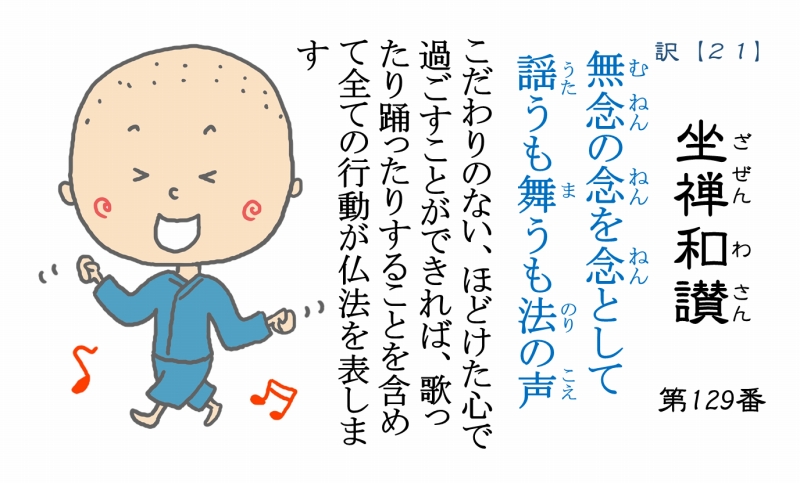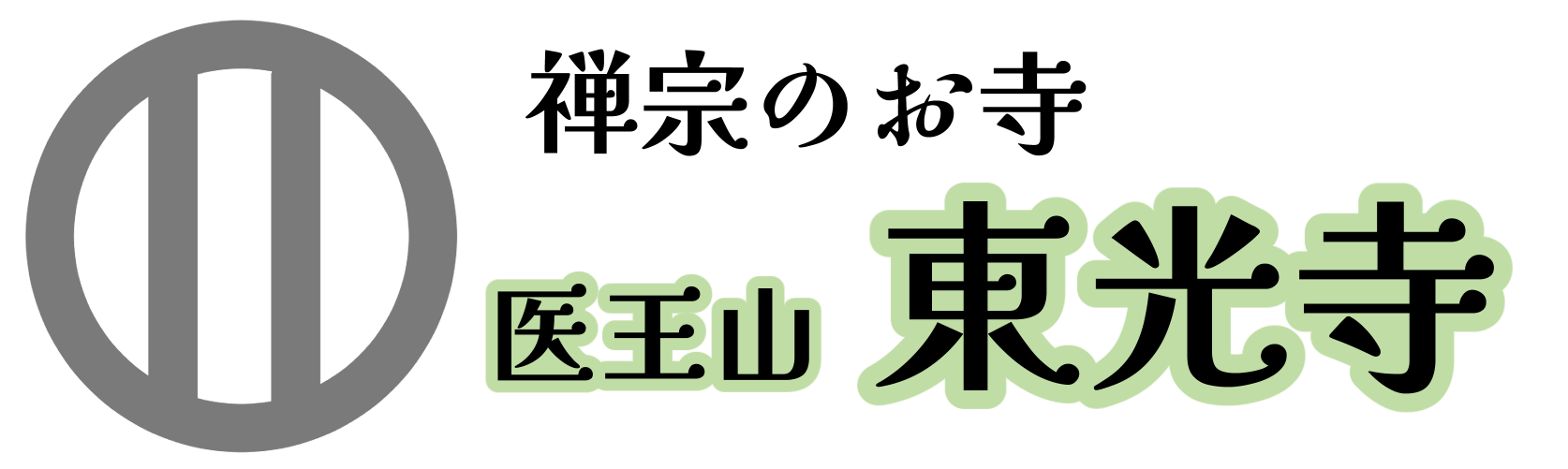僧侶とAIの共同作業が、お経を物語に変える夏㉙
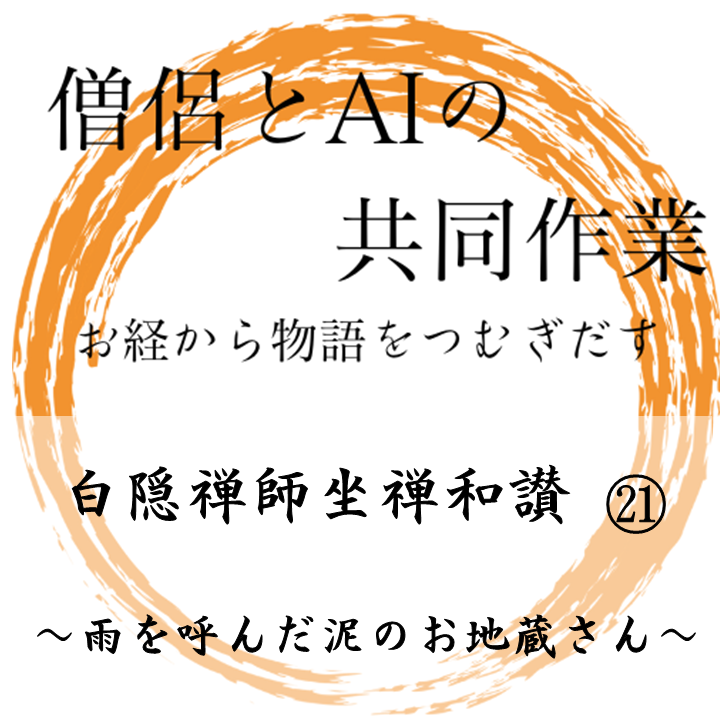
この物語は臨済宗でお唱えする「白隠禅師坐禅和讃」の一節から東光寺(静岡市清水区横砂)の僧侶とAIが会話をしながらつむぎだした物語です。
雨を呼んだ泥のお地蔵さん
森の村が、厳しい日照りに見舞われた、ある夏の年のことでした。
川は干上がり、木々は枯れ、動物たちは飲み水にも困るようになっていました。
村の長老であるサルは、みんなを集めて言いました。
「みんなで、雨乞いのお地蔵様を作ろう。心を込めて作れば、きっと天も応えてくださるはずじゃ。」
その言葉を聞いて、村の動物たちは、それぞれにお地蔵様を作り始めました。クマは、森の仲間たちのために、大きな丸太から、力強いお地蔵様を彫り上げました。キツネは、つるりとした石を磨いて、優しそうなお地蔵様を作ります。中でも一番器用なサルは、いくつもの木材を組み合わせて、まるで生きているかのような、見事な顔立ちのお地蔵様を作り上げていきました。
そんな中、村のはずれに住む、一匹のタヌキだけは、困っていました。彼は、とても不器用で、木を彫ることも、石を磨くこともできません。
「ぼくにだって、みんなを助けたい気持ちは、いっぱいあるのにな・・・」
タヌキは、自分にできることはないかと考え、干上がった河原へと向かいました。そして、まだ少しだけ湿っている泥を見つけると、それを両手で一生懸命にこね始めました。
彼は、誰かに褒められるような、立派なお地蔵様を作ろうとは考えませんでした。「こうすれば、雨を降らせてくれそうに見えるかな」といった、小手先の考えもありませんでした。
ただ、土の感触、水の匂い、自分の手の温かさ。そのすべてを感じながら、無心に、ひたすらに泥をこね続けたのです。
やがて、タヌキの手から生まれたのは、目も鼻もはっきりしない、ただの丸い泥の塊のようなお地蔵様でした。
しかし、そのお地蔵様を丘の上に運んでいくタヌキの姿を見たクマやキツネは、はっと息をのみました。
その不格好なお地蔵様は、技術を超えて、ただひたすらに森を憂い、雨を願う、純粋な祈りそのものの姿に見えたからです。
クマも、キツネも、サルも、そしてタヌキも。みんなが作ったお地蔵様が、丘の上にずらりと並びました。力強い願い、優しい願い、美しい願い、そして、純粋な願い。
その晩のことでした。みんなのたくさんの心が一つになったかのように、空から、ぽつり、ぽつりと、大粒の雨が静かに降り始めたのです。それは、乾ききった森の隅々までを優しく潤す、恵みの雨でした。
動物たちは、誰からともなく、丘の上に集まり、雨に濡れるお地蔵様たちの前で、静かに手を合わせました。特定の形や上手さにとらわれず、ただ無心に行うひたむきな行いもまた、天に通じる尊い祈りとなることを、みんなが感じていたのです。