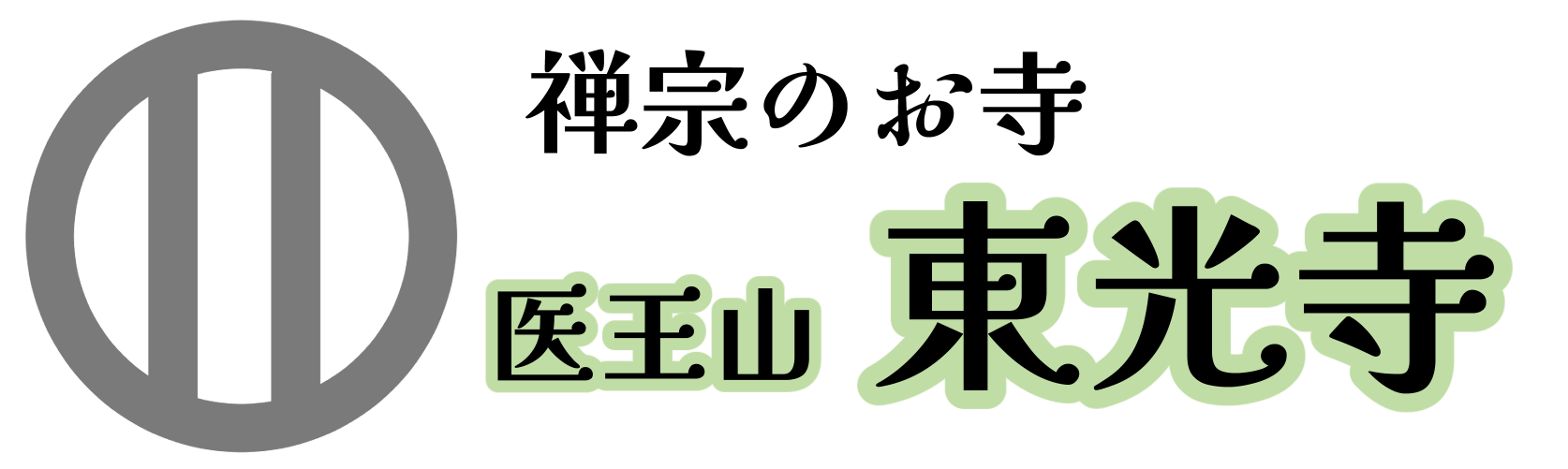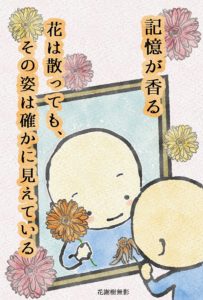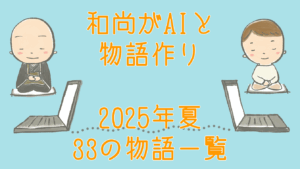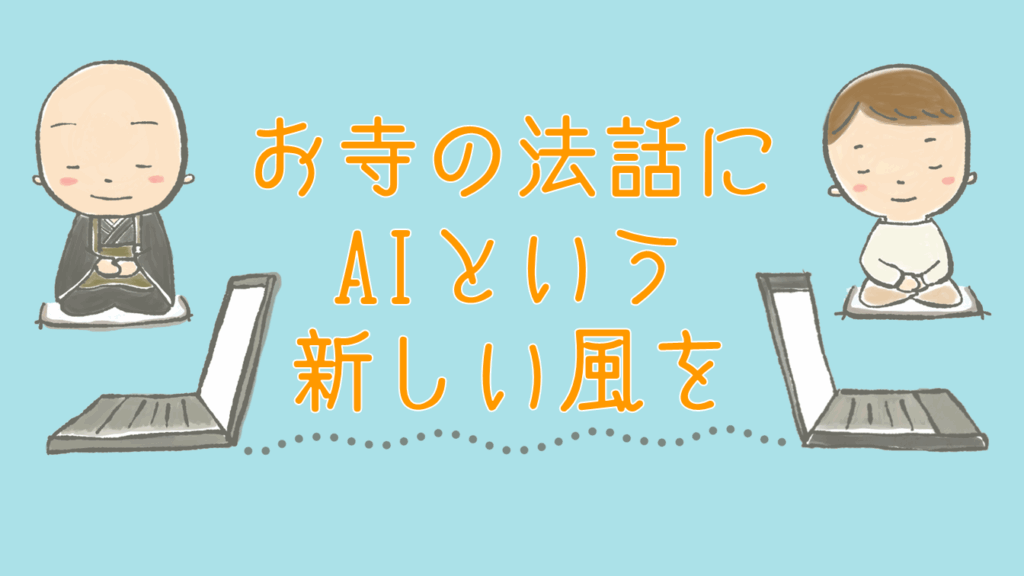
「和尚さん、今日は物語がないの?」
「和尚さん、今日は物語がないの?」
今年の夏休み子供坐禅会で、私が最も嬉しく、そして驚かされた坐禅会に参加してくれた子供からの言葉です。
その日は、行事などの都合で、法話・物語の音読をすることができませんでした。
すると、参加してくれていた子供の一人が、寂しそうに言ってくれたのです。
この夏休みに挑戦した「物語」を心待ちにしてくれていたことを知ったとき、私は新しい時代の仏教伝道の光を見出した気がしました。
新しい挑戦と、物語づくりのパートナー「GoogleのAI」
坐禅や写経の時間は、心を落ち着ける素晴らしい修行です。しかし、その後の法話の時間となると、子供たちがそわそわし始めてしまうのは、長年の課題でした。仏様の尊い教えを、どうすれば子供たちの心に届けることができるだろうか。
悩んだ末に私が挑戦したのは、白隠禅師の「坐禅和讃」やお盆という習慣を、子供向けの短い物語にして伝えることでした。
今年の夏休みの34回開催した坐禅会中に法話をする機会は33回ありました。
ですから、物語りも33回作ることになります。そして、その33にも及ぶ物語作りにおいて、私のパートナーとなってくれたのが、GoogleのAIでした。
AIとの対話 — 違和感から調和へ
最初は、戸惑いの連続でした。GoogleのAIに
「白隠禅師の『水と氷の如くにて』という部分を物語にしてください。〇〇といった例話や、主人公は◇◇で、△△という流れで作っていきましょう。」
といくつかの条件を入れてお願いすると、AIはたちまち、流れるような美しい物語を紡ぎ出します。その速さと発想力には驚かされました。
しかし、その完璧に見える文章には、当初、私が大切にする仏教や禅の心から見ると、違和感がありました。
例えば、初期に作成した「森の音楽コンクール」の物語では、ある鳥の歌の素晴らしさを伝えるために、別の鳥を「歌が下手な悪役」として対比させる構成を提案してきました。他者と比較して優劣をつける手法は、禅の教えとは相容れません。
「比較ではなく、主人公の内面的な成長に焦点を当ててください。」
私がそう指示すると、GoogleのAIは即座に物語を修正します。まるで、人間の弟子が師匠の教えを吸収していくかのようでした。
対話は、1つの物語を作るために何度も何度も繰り返しました。
この対話を繰り返していくことで、夏休みの終盤で、「無二無三の道(ただ一つのまっすぐな道)」をテーマに物語をを作った際には、私が修正の指示を出す前に、AIは自ら、罪を悔い改めた主人公が、過去を乗り越えるのではなく、その厳しい報いをすべて受け入れながらも善行を続けるという、非常に深く、仏教的なテーマを織り込んだ物語を提案してきたのです。
初期の頃の「比較」や「競争」といった発想は、いつの間にか私と対話を続けたAIから無くなっていました。
AIが私の考えを学習したのか、それとも私がAIとの対話を通して、子供たちに伝えるべき物語の本質をより明確に表現できるようになったのか。
おそらく、その両方なのでしょう。33話の物語作りを通じて、私とGoogleのAIの思考は、ゆっくりと調和していったのだと思います。
子供たちの変化、そして未来へ
その成果は、子供たちの姿に、表れました。
これまで法話が始まると飽きてしまっていた子も、「次はどんな動物が出てくるの?」と身を乗り出し、物語の世界に聞き入ってくれました。
読み聞かせが終わった後、私が「このお話はね…」とその物語に込められた仏様の教えを解説するまで、しっかりと話を聞いてくれるようになりました。
物語にすることで、仏様の教えは、子供たちの心へ、まっすぐに届いていく。そして、AIという現代の技術が、新しい扉を開いてくれたのです。
AIと人間が手を取り合って、仏様の教えを次の世代へ伝える。そんな未来が、もう始まっているのかもしれません。
来年の夏も、また新しい物語を携えて、子供たちの純粋な瞳に会えることを、今から心待ちにしています。この尊い挑戦を、これからも続けていきたい。そう強く願っています。