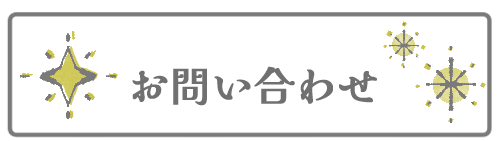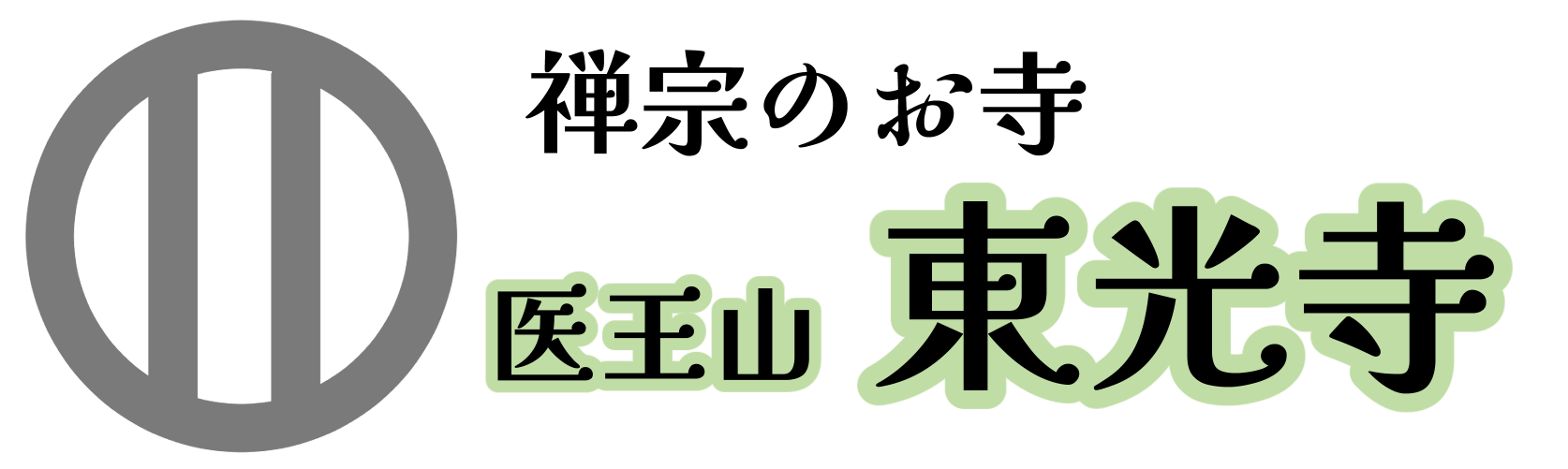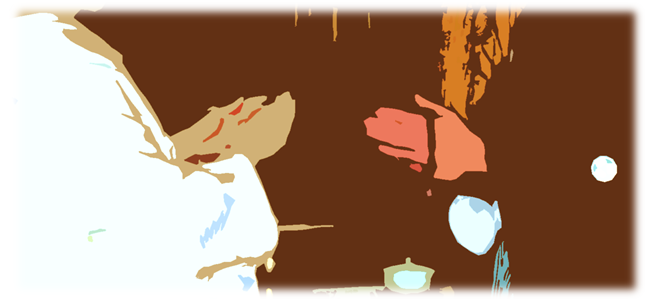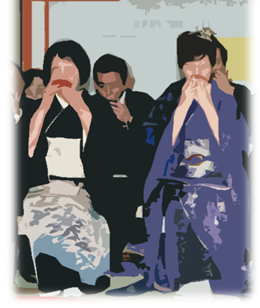日本で古くからある、
最も歴史のある結婚式の一つが仏前結婚式です。

神聖な尊い心を得る
洗心せんしん
心の拠り所を明らかにする
帰依三宝きえさんぼう
具体的な生き方を自覚する
授戒じゅかい
幸せな家庭を築き、
社会への貢献を誓う
誓願せいがん
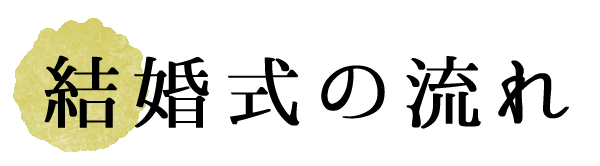
基本的な例です。ご相談に応じて内容の変更は可能です。
一
和合の茶礼
-わごうのされい-
禅宗の習慣で、様々な行事のけじめとして、一堂に会して一つの釜で沸かしたお茶を頂きます。これを和合の茶礼といい、
「この出会いは二度とない一期一会の出会いであり、この出会いを大切にします。」
という想いが込められています。
仏前結婚式でも同じように、式の始まる前に参列者全員がお茶を頂きます。
両家の親族や関係者が集まる機会は多くはありません。その貴重な時間を大切にし、御両家 の益々の和合を祈念するための茶礼でもあります。
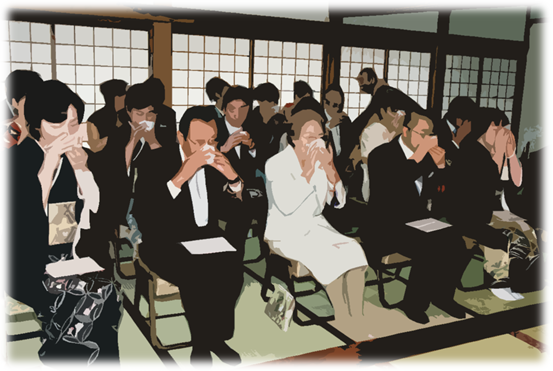
二
献花
-けんか-
結婚式が始まると、仏様の慈悲を表すお花が献じられます。
この役目を「天童(てんどう)・天女(てんにょ)」と呼び、ご親族の中にお子様がいらっしゃった場合、担当していただくことが多いです。
天童・天女:仏教の守護神や天人などが子供の姿になって人間界に現れたもの。

三
焼香・三拝
-しょうこう・さんぱい-
戒師が新郎・新婦、参列者を代表して、焼香・三拝をし、場を清めます。
戒師(かいし):結婚式を執り行う僧侶のこと。
三拝(さんぱい):非常に丁寧なお参りを三回行うこと。
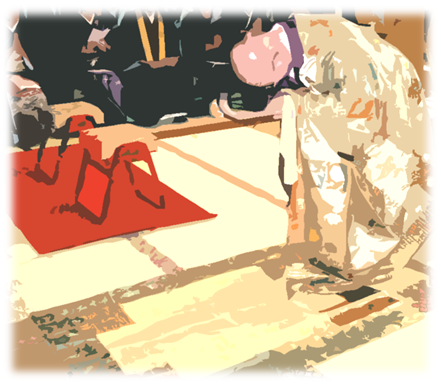
四
啓白文奏上
-けいはくぶんそうじょう-
啓白文とは、
結婚の儀を執り行うことを宣言し、新郎新婦の二人の将来に幸あれ
という祈りが込められたものであり、戒師が読み上げます。

五
清めの式
-きよめのしき-
懺悔文(さんげもん)をお唱えし心を清めます。
続いて、香水(こうずい)を注がれることにより身体を清めます。
香水:白檀(高級なお香)などの香りのよい香木で作られたもの
清められた心と身体で三帰戒(さんきかい)をお唱えし、できるだけ五戒を守ることを誓います。これにより、「自分にできる範囲で積極的に良い習慣を積み上げていこう。」と心に刻みます。
これから長い時間を共にする新郎新婦にとって、非常に大切な教えであり、良い夫婦関係を保つ土台となります。

六
睦みの式
-むつみのしき-
寿珠(じゅず)の授与・交換を行います。
これにより、お互いを尊敬しあい拝み合う気持ちを持つことができます。
ご希望により、寿珠交換のあと、指輪の交換もすることができます。
お数珠を手にしての指輪の交換もよい思い出に残ることと思います。
七
誓いの言葉
-ちかいのことば-
「誓いの言葉」を本尊様の前で読み上げます。
本尊様・ご先祖様に結婚したことを報告すると同時に、今後どのように夫婦として生活していくかを、自分自身をはじめ、すべての人に誓います。

八
寿杯
-じゅはい-
新郎、新婦が三三九度の杯を交わします。
その後、ご両家固めの杯の儀を行います。
ちょっと豆知識
~三三九度について~
三三九度は、その名の通り 新郎新婦が三つ組の杯で、それぞれの杯を3回ずつ合計9回やり取りすることです。
仏教では様々な法要の際に、礼拝(らいはい)をします。この礼拝の中で最も丁寧な礼拝と言われるのが、両ひざ・両ひじを地に着け、さらに頭も地につける五体投地(ごたいとうち)です。
通常、「五体投地」は3回が1セットで、この1セットを3回行います。つまり五体投地を全部で9回行います。
白無垢などでは動きづらいため、結婚式では五体投地の代わりに、絆を深める力を持つ杯で行うようになり、これが、「三三九度」の起源ともいわれています。
「五体投地」は謙虚になるために行うものですので、結婚式で三三九度を行うことにより、新郎新婦は謙虚な気持ちで、相手を想い、大切にし、絆を深めていくことができるのです!
九
報恩の黙想
-ほうおんのもくそう-
戒師からの「祝いの言葉」、結婚証明書への署名・授与ののち、生かされている報恩と、新郎新婦の幸せを祈り、一同一分間の黙想をします。これを報恩の黙想といいます。
式を納めるにあたり、
「自分たちの、このおめでたい功徳をが、私たち人間をはじめ生きとし生けるものすべてのためになり、皆が幸せになりますように」
との願いを込めて、参列者全員で四弘誓願(しぐせいがん)・普回向(ふえこう)をお唱えいたします。


わたしたち、
お寺で結婚式を挙げました
K様ご夫妻
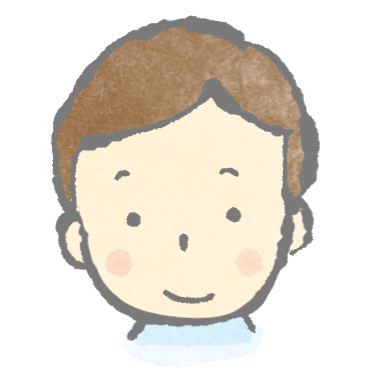
事前に仏前式の練習があり全体の流れと雰囲気が分かり易かったです。
また、聞き慣れない仏教用語と作法の細かな説明があり理解出来ました。
初めての仏前式でしたが、司会の進行が上手くて楽でした。
列席者にも式次第が用意されて、仏前式の内容が分かり易かったと思います。
普段は仏様の前に長時間居ることがないので心が清らかになった様に感じます。
人生の節目として有意義な行事を無事に行えた事が良かったです。
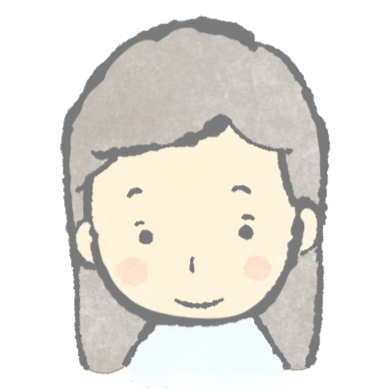
準備いただいた皆様に感謝です。落ち着いて式に臨めました。
先祖・家族に感謝できる式、家族,皆様の今後の発展を祈ることができる式という点が良かったです。
指輪の交換(着用)を考えていない私たちにとって,数珠のプレゼント・交換は嬉しかったです。また、戒師のサインが入った証明書も記念になります。
さらに、具体的な指針(五戒)が示され,今後の生活に役立ちそうに感じました。
伝統ある白無垢を着ることができ、また、親族の着物も合う会場でした。
家族・親族からの三三九度や献花は嬉しかったです。
式後に全員で写真が撮れて記念になります。
Y様ご夫妻
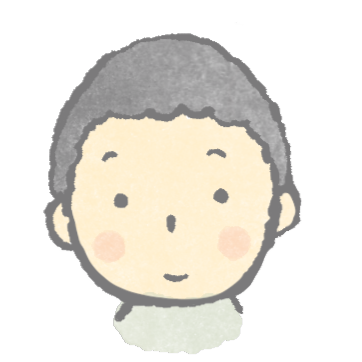
お寺で結婚式をすることになり、友人たちも参列を希望してくれました。
初めての仏前結婚式への参列に「作法などまったくわからない」と戸惑う友人たちでしたが、式が滞りなく終了すると
「いい雰囲気だったね!」
「何をやっているのか説明をしっかりしてくれたので分かりやすかった。」
「知っている和尚さんがいると、なんだか安心するね。」
などと良い感想を多く行ってくれました。
中でも
「新鮮な感動をありがとう。」
と言ってくれた友人の言葉が印象的でした。

人生の節目である結婚の報告をご先祖様にする、というところが他の式にはない特徴であり、いいな、と思いました。
私の結婚式をとても楽しみにしていてくれた祖父が、式の数か月前に急逝したのですが、仏様の前での結婚式に、祖父も参列してくれているような気がしました。
お数珠の交換や、三三九度でお酒を注ぐ役を私の従姉と夫の幼馴染が務めてくれたこともよい思い出になりました。
指輪の交換もできて、大満足です!!
普段はなかなか触れることのない仏様の教えですが、丁寧に説明していただくと、日々の暮らしにも生かしていけることが多いことを知りました。
このような機会に恵まれたことに感謝です!
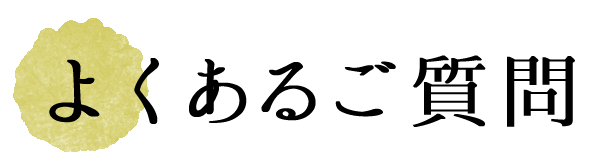
-
東光寺の檀家ではないのですが、結婚式を挙げることはできますか?
-
可能です。
仏前結婚式はご縁に感謝し、ご先祖様にも人生の節目を報告し、今後の生き方を誓う場です。これまでの宗旨・宗派は問いません。
-
写真撮影・動画撮影はできますか?
-
もちろん可能です。人生の節目である一日をぜひ記録に残してください。
-
ウェディングドレスを着ることはできますか?
-
もちろん可能です。和装、洋装、ご希望に合わせてお選びください。
-
仏滅に結婚式を挙げても大丈夫ですか?
-
仏滅、大安などの六曜は仏教と特に関係はございませんのでお式を挙げることは可能です。
ただし、ご両親、ご親戚など日取りを気にされる方がいらっしゃる場合は事前に説明して了承を得ておくことをおすすめいたします。
-
式の時間はどのくらいですか?
-
式の進め方や参列者の数などによって前後しますが、開式から閉式まで概ね30分~40分程度だとお考え下さい。ただし、新郎新婦には様々な準備がありますので、当日は早めに来ていただくことになります。詳しくは打合せの際に相談をさせていただきます。
-
参列可能な人数について教えてください?
-
本堂内には60名ほどお席を用意することが可能です。詰めて椅子を並べますと100名~120名まで入ることができます。
-
新郎新婦のみで結婚式を挙げることは可能でしょうか?
-
もちろん可能です。
人前では恥ずかしく感じる、大げさにしたくない、などいろいろな理由があるかと思います。お二人に合わせてお式を挙げさせていただきます。
-
事前に必要なことはありますか?
-
前日までに一度は流れを確認していただくなどのために打ち合わせをいたします。また、聞きなれない仏教用語等についてもご説明いたします。意味を知ることでさらに気持ちのこもったいいお式になることと思います。
-
参列者はお数珠が必要ですか?
-
お持ちであればご持参いただくようご案内ください。必ず必要、というわけではありません。
そのほか、ご不明な点等ありましたら、遠慮なくご連絡ください。